2013年03月15日
連載小説「龍の道」 第107回
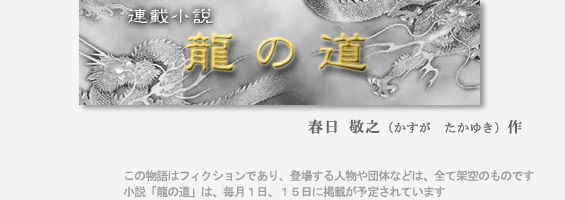
第107回 鞆 絵 (ともえ)(5)
「さて、もう講義はこの辺りで切り上げて、いよいよ実地訓練に入るワケですね!!」
きらきらと目を輝かせて、宏隆が言った。
「あはは、やっぱり男の子ねぇ、早く銃を撃ちたくて仕方がないみたいね?」
「そりゃそうですよ、男だったら誰だってそうです。秘密結社に入ったおかげで、ハワイに行かなくても実銃が撃てるんですからね。ウチの父なんか、家の地下に射撃場を造るって、本気で考えていたみたいですから」
「まあ・・いくらお父様がご立派な方でも、日本ではそれはマズいんじゃないの?」
「そうです。だから父はオーストラリアの別荘の地下にそれを造るって言ってました」
「はぁ・・何ともまあ、スゴイ親子だわねぇ・・・・」
さすがの宗少尉も、その話には呆れている。
「ところで─────────────────」
宗少尉が何か言いかけようとするが、
「えーっ、まだ銃のウンチクが続くんですかぁ・・?」
それを遮って、宏隆が不服そうに言う。
「蘊蓄じゃなくって、銃を扱う者に必要な ”心構え” を話してるのよ!」
「そりゃそうでしょうけど・・そうだ!、だったら、講義と実技を交互にやりませんか?
(いい加減にしないと、読者も飽きるだろうしサ・・)」
「あのねぇ、大事なコトだからマジメに聴きなさいってば!!」
「分かりましたよ、もぉ・・ハイ、どうぞ。御説をば拝聴いたしますデス」
「オホン・・で、さっきアメリカの銃社会について話したけれど、まだ続きがあるのよね」
「あ、それなら、もう少し聴きたいですね」
「ムッ・・それなら、とは何よ。それなら、とは!!(ゴラぁ・・!)」
「あ、ごめんなチャイナ、失言ッス」
「なんか猛王烈クンみたいね・・・・以前、あるアメリカの田舎町に行ったときに、友人と住宅街を歩いていたんだけれどね。あの国の住宅って、どこでも道路と境界線がなくって、ただ芝生が植わっていて、玄関へのアプローチが続いている家が多いでしょ?」
「ふむ、そうですね────────────」
「友人と並んで歩くにはちょっと歩道が狭かったので、つい芝生の上を歩いていたのよ」
「ふむふむ、芝生の上は気持ちが良いですよね。それがどうかしたんですか?」
「その時、友だちに注意されたのよ。 ”麗華(宗少尉の名前)、そんな所を歩いちゃダメよそこの家の窓からいきなりズドンとやられても文句は言えないわよ。ここじゃヨソ者はすぐに見分けが付くからね。敷地内に無断で入った余所者をいきなり撃ち殺しても、警察は何も文句を言わないよ!” ・・ってね」
「いきなり撃ち殺す?・・ひえぇ、何てぇクニなんだっ!!」
宗少尉の話は決してオーバーではない。この物語から20年経った1992年、アメリカに留学していた16歳の日本人高校生が射殺された衝撃的な事件は、まだ読者の記憶に新しいと思うが、それでも20年も前の出来事なので、知らない方のために少し解説しておきたい。
AFS(国際教育交流団体)を通じてルイジアナ州バトンルージュに留学していた服部剛丈(はっとりよしひろ)君は、寄宿先のホストファミリー(留学生を受け容れる家族)と共にハロウィンのパーティーに出かけたが、訪問する家を間違えてしまったため、その家の住人であるロドニー・ピアーズから侵入者と判断され「Freeze(動くな)!」と警告された。
しかし服部君にはその意味が分からず、「パーティに来たんです」と言いながらそのまま笑顔で住人に歩み続け、玄関先2.5メートルの距離でマグナムを装填したS&Wを発砲され、救急車で運ばれる途中、出血多量で死亡した。
発砲したピアーズ被告(30才)は、日本の傷害致死罪に相当する「計画性のない殺人罪」で起訴されたが、バトンルージュ郡地方裁判所の陪審員12名は全員一致で正当防衛・無罪の評決を下した。弁護人は最終弁論で「玄関のベルが鳴ったら誰に対しても銃を手にしてドアを開ける法的権利がある。それがこの国の法律というものだ」と語った。
なお、ルイジアナ州の法律では屋内への侵入者に対する発砲は容認されているが、服部君は屋内には入っていない。
その後の遺族が起こした民事裁判では、ピアーズ被告が自宅に何丁も銃を持つガンマニアであり、しばしば自宅の敷地内に入ってきた猫や野良犬を射殺したり、事件当日も酒を飲んでいたことなどが証明されたため、正当防衛とは認められないとして、判決では65万3千ドル(約七千万円)を支払う命令が出され、同州の高等裁判所も控訴を棄却したため、ピアーズは破産することになった。
服部君の両親はAFSや友人たちの協力で「アメリカの家庭から銃の撤去を求める嘆願書」の署名活動をし、一年あまりで170万人を超える署名を集め、1993年11月、ビル・クリントン大統領に署名を届けるために面会した。また服部夫妻がワシントンD.C.に滞在中、銃規制の重要法案である「プレディ法」が可決された。
この事件は後にドキュメンタリー映画にもなり、被害者の母親が事件の顛末を記録した著書をはじめ、国内外の様々な人による著作が多数存在している。
「だからと言って、銃規制を厳しくすれば良いという問題でもないのよね─────────」
ちょっと中空を見つめるような目をして、宗少尉が言った。
「と、いうと?」
「たとえば、今度のアメリカの大統領選挙では、有力な候補者が選挙運動中に ”銃規制” に前向きな発言を繰り返していたけど、それにともなって、異常なほど銃と弾薬の売れ行きが上がっていたのよ」
「えっ、それって変ですよね。反対なんじゃないの?」
「理由は簡単よ。銃規制に前向きな有力な候補者が大統領になったら、銃を買うことができなくなるかもしれない、という危機感が多くのアメリカ人を駆り立てて、銃と弾丸を買いに走らせるってコトね」
「へぇー、日本じゃ全く考えられないことですねぇ」
「それは、陰では ”恐怖のバブル” とか ”恐怖刺激政策” などと揶揄されているわ。ま、その背景には、全米ライフル協会(NRA=National Rifle Association)が多額の資金を投入してPR作戦を展開している、ということも大きく影響しているんだけれどね」
「ははぁ、何だか話が怪しくなってきましたね────────────」
「全米ライフル協会は、あらゆるメディアを使って、”次期大統領はアメリカ人から自由を奪い、銃を持つことを禁止しようとしている史上最も銃を嫌っている大統領だ、いま銃を買っておかなくては二度と買えなくなるぞ!” ・・などと言って扇動しているワケよ」
「その結果は、どうなったんですか?」
「スターム・ルガー社では前年比で純利益が4倍になり、株価は80%以上も上昇したわ。
スミス&ウエッソン社の株価も、およそ三倍まで跳ね上がった。まあ、全米ライフル協会というのは歴代大統領のほとんどがメンバーになっているからホントに怪しいものだけれど。何よりその大統領自身、オフの日はクレー射撃に興ずるような人だからね・・・」
「しかし、何につけても、すごい国だなぁ─────────────────」
「こんな話をするとアメリカの銃社会ばかりが問題にされているみたいだけれど、実際にはアメリカよりベネズエラやブラジルの方が銃による死亡率は高くて、人口比でアメリカの三分の二しかないブラジルは、アメリカより遥かに銃による死亡者が多いのよ。ベネズエラの成人男性の死亡原因の第一位は、何と ”銃による殺害” なんだから」
「死亡原因の第一位が、銃による殺害?!・・・ガンとか、心臓病とかじゃなくって?」
「そう、昭和元禄・平和ボケのニッポン人にはちょっと衝撃的でしょ。ベネズエラにはあまり行かない方がいいカモね。まあ、病めるアメリカは ”悪しき銃社会” としてよく槍玉に挙げられるけれど、世界的に見ると銃の所持を認めている国や地域はとても多くて、日本みたいに所持が非常に難しいという国の方が珍しいのよ」
「本当ですか────────────?」
「国によって差はあるけれど、ヨーロッパの多くの国では拳銃やライフルの所有を認めているし、スーパーで銃が売っているようなアメリカと比べれば所持する条件は厳しいけれど、日本よりは遥かに許可が取りやすいようになっているわね。ただ、イギリスのように日本と同様の厳しい規制を行っている国も存在するけれど。
東南アジア、南米、アフリカなどに至っては銃が市場にゴロゴロ出回っている状態ね。フィリピンなどでは、ごく普通の町工場が銃を密造して海外に売りさばいている。同じ東南アジアでも、シンガポールは日本同様に厳格な規制をしているけどね。
中東やアフリカなど内戦が多い所では何処でも拳銃やライフルが簡単に手に入って、小学生くらいの子供が裸足でライフルを担いで歩いているのを当たり前の光景として見かける。そしてひとたび犯罪が発生すればたちまち市街戦になって、大人も少年も入り乱れてガンガン撃ち合うのが、ごく普通に見受けられるのよ」
「うむむ、そんな話を聞くと、たとえ平和ボケだろうが昭和元禄だろうが、とりあえず日本が平和で良かったと思えてきますが─────────────────」
「そうなると、その問題をどうするかというのが国際社会の課題よね。それらは正常な現代社会の文明や生活とは、とても言えないでしょうから」
「日本人の感覚だと、銃の犯罪が起こるのなら銃を規制すれば良い、ということになると思います。けれど、例えばアメリカという国は、もともと色々な国から移住してきた雑多な人たちで造られた国家で、彼らの侵略を阻止しようと命懸けで戦った先住民族なども存在したわけですから、建国当初の ”自分の身は自分で守る” という精神が根強いんでしょうね」
「米国でよく使われるのが ”もし貴方が強盗をするとしたら、銃で武装をしている家と、全く銃を置いていない家の、どちらをターゲットにして狙うだろうか?” っていうフレーズ。
それに、銃を乱射した大事件の後には、必ずテレビ局が ”このような銃の犯罪が繰り返し起きてしまうのは何故でしょうか?” と問いかけて世論調査番組を放送するけど、”銃が簡単に手に入るため” だと回答する人は、常に全体のわずか2割にも満たないのよ」
「それ以外の人は、どんな回答をしているんですか?」
「犯罪者の人格の問題だとか、子供の頃からのシツケの問題だとか、いろいろね・・・」
「うわぁ、やっぱり日本とはちょっと考え方が違うなぁ!」
「銃の所持を認める国は、歴史的、伝統的に銃がその国にとって象徴的な意味合いを持っているからよね。日本だと、たとえば日本刀の所持を許可制度まで廃止して一切禁止するということになったら、日本刀を持つ武術家や愛好家だけでなく、日本の伝統文化を大切にする一般人からもかなりの反発が出ることは必至でしょう?、それと同じことよ」
「なるほど、そう言われると少し解るような気がしてきます。銃社会と言っても、ひと言でその善悪を決めることの出来ない、様々な問題が絡んでいるんですね」
「そうね。さっき出た全米ライフル協会などは、実質的な圧力団体でもあるわけだし・・」
「圧力団体?、銃の愛好家が造っている団体じゃないんですか?」
「ある面ではもちろん、銃愛好家の市民団体であることには違いないのだけれど。
NRAは南北戦争に勝った北部出身者や銃の販売業者、銃愛好家によって1871年に設立された団体よ。会員数400万人、スローガンは ”銃が人を殺すのではない、人が人を殺すのだ” という名文句。アメリカ合衆国憲法修正条項第2条にある、”武器を所持して携帯する権利” を根拠に、銃規制に反対している団体よ」
「ははは、そりゃ名文句ですね、うまいこと言うなぁ・・」
宗少尉の言う、NRAのその根拠主張に対しては、国民の無制限な武装権を認めたものではないと批判する意見も米国内に多くあったが、2008年7月、アメリカ連邦裁判所は同条項を「個人の武装権を認めたもの」とする判決を示している。
「・・・まあ、アメリカなどは、教会の牧師さんでも銃を持っているような社会だからね。警官に職務質問を受けた時には絶対に動いてはいけないというのが鉄則。間違っても上着の内ポケットや、腰の後ろに手を回すような仕草をしないことが大切ね」
「それで撃たれても文句は言えない、と?」
「もちろんそうよ。実際にそれでズドンと撃たれる人は沢山いるワケだから。アメリカでは殺傷能力の無いオモチャの銃で遊んでいた子供を、”今まさに銃を発砲しようとした凶悪犯” として射殺するような事件が後を絶たないのよ。だから遊戯銃は実銃と混同されるような外観にすることを厳しく禁止している。これは水鉄砲に至るまで適用されているのよ」
「いくら何でも、日本じゃ水鉄砲までは規制しませんね。アメリカはそれほど病める社会だというワケですね・・・そう言えば、この地下訓練場にある格闘室にも、青く塗られた訓練用の拳銃がいくつか置いてありますね」
「アメリカでも台湾でも、警察や軍隊で使われる訓練用の模造銃は、容易に本物と比較できるように、材質とは関係なく必ず全体を青や赤で塗る義務があるの。それらはブルーガン、レッドガンと呼ばれているわね」
「ただ訓練用の銃として区別するように塗られているんだと思っていました。そこには明確に実銃と区別されなければならない、切実な理由があったワケですね?」
「そういうコト。ブルーガンと言えば、スポーツ格闘技などで ”銃を向けられたらどう対処するか” などという護身術的な練習があるみたいだけれど、実銃を持ったことも撃ったことも無い、ましてや軍事訓練経験があるわけがない、というレベルの人がいくら銃の対処法を練習しても、ほとんど無駄なコトね。いくら格闘技をやっていても、素人は本モノの危機を実感したことなんか無いワケだから、銃を撃ったことも、撃たれたことも、ナイフを持った複数の敵に囲まれたことも無いんだったら──────────────」
「ムリですよ、そんなの。平和ニッポンでは滅多に起こり得ないことなんだから。銃の対処法を練習するのに使うゴムのダミーガンだって、日本じゃ黒く塗られていますからね」
「でも、その ”危機” を実感したことが有るか無いかでは、武術修行に大きな差が出るのよ。ナイフ対処法も、しょせんはスポーツ格闘技のレベルが関の山でしょうね」
「むぅ・・厳しいお言葉ですが、その通りでしょうね。スポーツ格闘技と本物の武術とは、まるで中身が違います。まあ、スポーツ格闘技というのは、あくまでも競技のための技術を磨いていくわけですから、実際の戦闘とは全く考え方が違うわけです。スポーツの中で実戦での本物の強さを身に着けていくのは、たいへん無理があると思いますね」
「ヒロタカみたいなのは特別ね、そんな経験は大金を積んでも、なかなか味わわせて貰えないことよ」
「おかげさまで・・たとえケンカで百戦無敗でも、そういうことは決して解らないですね。ケンカの若大将なんて言われて良い気になっていた僕も、王老師と出会って痛い目に遭わされて、ようやくそれを実感し始めた程度です。その後も、本物の兵士である宗少尉や陳中尉とも手合わせして頂いたり、プロに襲撃されたり拉致されるという経験をして、ようやく武術や戦闘についての考え方がずいぶん変わってきました」
「ふぅん・・講義を聴くのは苦手みたいだけどねぇ・・・」
「あ・・そ、それを言われると──────────────」
「アハハハハ・・・・」
「はははは・・・・」
「さてと、それじゃ、ひとまず射撃訓練に入るとするか!」
「やったぁ、待ってました!!」
(つづく)
*次回、連載小説「龍の道」 第108回の掲載は、4月1日(月)の予定です
コメント一覧
1. Posted by bamboo 2013年03月17日 23:10
あの事件からもう20年以上経つのですね…。まだ学生でしたが、よく覚えています。遺族の悲しむ顔も、ロドニー氏の態度も。
武器や兵器は、どうしても経済や政治と結びついてしまいますね。とくにアメリカの場合、どうしても減らせない事情をお持ちのようで。それを想うと、先の事件も重なり悲しい気持ちになります。
「blood diamond」は数年前に観ていましたが、現実にアフリカ中で起きている紛争のほんの一部だそうですね。世界は紛争だらけで、その背後にはいつも大きな力が動いている。しかも昔から…!アフリカや中東に比べれば東南アジアなんかまだ静かな方ですね…いや最近はそれもなんチュウカ怪しい。 あぁ…ホントに悲しくなってきたのでこの辺で終わります…。
近いうち、神戸に行こうと計画しております。龍の道でご紹介頂いたお店やホテル・名所などを訪ねようと思います。
武器や兵器は、どうしても経済や政治と結びついてしまいますね。とくにアメリカの場合、どうしても減らせない事情をお持ちのようで。それを想うと、先の事件も重なり悲しい気持ちになります。
「blood diamond」は数年前に観ていましたが、現実にアフリカ中で起きている紛争のほんの一部だそうですね。世界は紛争だらけで、その背後にはいつも大きな力が動いている。しかも昔から…!アフリカや中東に比べれば東南アジアなんかまだ静かな方ですね…いや最近はそれもなんチュウカ怪しい。 あぁ…ホントに悲しくなってきたのでこの辺で終わります…。
近いうち、神戸に行こうと計画しております。龍の道でご紹介頂いたお店やホテル・名所などを訪ねようと思います。
2. Posted by 円山玄花 2013年03月18日 15:17
日本と欧米の危機感の違い、そして危機管理の違いを、改めて認識させられる思いがします。
結局、拳銃だから危険だとか、刃物は何センチ以上は危険だという問題ではなくて、
殺傷能力を有する道具を自分が持つという意味を分かり、その心構えがあるか否かで、
「危険」か「安全」かが決まるのですね。
銃社会について学ぶことで、自分が武器を所有し、それに熟達するために訓練するということの
意味と意義とが、より鮮明になりました。
次回も楽しみにしています。
結局、拳銃だから危険だとか、刃物は何センチ以上は危険だという問題ではなくて、
殺傷能力を有する道具を自分が持つという意味を分かり、その心構えがあるか否かで、
「危険」か「安全」かが決まるのですね。
銃社会について学ぶことで、自分が武器を所有し、それに熟達するために訓練するということの
意味と意義とが、より鮮明になりました。
次回も楽しみにしています。
3. Posted by 太郎冠者 2013年03月18日 21:03
一個人の意識でさえそうなのですから、アメリカが多大な軍事費を使う理由がわかる気がしますね。
防衛に関する考え方が、日本とは大きく違うんですね。
稽古をしていて感じるのは、ナイフへの対処法を訓練するにしても、型通りにやっているだけではわからないことは多いということでしょうか。
構造をひたすら稽古することで、動いたときに自然と型のような動きが出るのは、個人的にはすごく面白いことのように感じます。
(師父は後ろで「まだまだダメだなぁ」と呆れているのですが(笑))
あと、本物のナイフで稽古をしてみるのも、…面白かったですね。自分の動けなさが分かるというものです。
いかに日常で感覚が鈍っていることでしょう!
防衛に関する考え方が、日本とは大きく違うんですね。
稽古をしていて感じるのは、ナイフへの対処法を訓練するにしても、型通りにやっているだけではわからないことは多いということでしょうか。
構造をひたすら稽古することで、動いたときに自然と型のような動きが出るのは、個人的にはすごく面白いことのように感じます。
(師父は後ろで「まだまだダメだなぁ」と呆れているのですが(笑))
あと、本物のナイフで稽古をしてみるのも、…面白かったですね。自分の動けなさが分かるというものです。
いかに日常で感覚が鈍っていることでしょう!
4. Posted by とび猿 2013年03月18日 23:44
留学生が銃で撃たれた事件は、当時、とても驚きました。
当時の自分が一番初めに思ったことは、「何故その程度のことで撃たれたのか?」ということでした。
何しろ、当時田舎では、昼間は玄関は開けてあるのが普通で、例えば回覧板などでも、ポストではなく、訪問者がインターホンも使わず玄関を開け、声を掛け、返事がなければそこに置いていくようなことがよくありました。
そこから見れば、まるで別世界の事のように思えます。
それで生活が回っていた日本人のモラルは素晴らしいと思いますが、一度外へ出たら、知らなかったでは済まない事が出てきます。
そして、日本の状況も変わってきていると感ます。
扱う人に依って、武器は凶器にもなれば自衛の手段にもなり、オモチャにもなると思います。
もっと一人一人が自衛ということを考えていかなければならないと思いますし、武術を学ぶ者であれば、尚更正しく理解していかなければならないと思います。
当時の自分が一番初めに思ったことは、「何故その程度のことで撃たれたのか?」ということでした。
何しろ、当時田舎では、昼間は玄関は開けてあるのが普通で、例えば回覧板などでも、ポストではなく、訪問者がインターホンも使わず玄関を開け、声を掛け、返事がなければそこに置いていくようなことがよくありました。
そこから見れば、まるで別世界の事のように思えます。
それで生活が回っていた日本人のモラルは素晴らしいと思いますが、一度外へ出たら、知らなかったでは済まない事が出てきます。
そして、日本の状況も変わってきていると感ます。
扱う人に依って、武器は凶器にもなれば自衛の手段にもなり、オモチャにもなると思います。
もっと一人一人が自衛ということを考えていかなければならないと思いますし、武術を学ぶ者であれば、尚更正しく理解していかなければならないと思います。
5. Posted by まっつ 2013年03月19日 00:03
学生の時分に山登りをしていて、
他の登山者も居ない奥深い山に一人で踏み込んだ際は、
常には感じない強い危機感を覚えました。
怪我を負ったり、道に迷ったり、
ペース配分を誤って行動できなくなったりしたら、
遭難して命に関わるので、常よりも一歩を慎重に運び、
頻繁に地図を確認し、ペース配分にも気を配りました。
危機感があれば、それらの注意は自然と働くようでした
武術に関しても危機感の有無は、
当然、稽古の成否に直結するに違いないと思います。
ただそれは頭で分別されているだけで、
実感として迫ってきているかを自らに問えば、否です。
稽古のルールに守られている意識が先ずあり、
危機から来る注意の働きは鈍い状態です。
日常の生活に追われ流されて、
本当の危機から遠い位置に居る現状の見直しが必要なのだと、
強く感じました。
他の登山者も居ない奥深い山に一人で踏み込んだ際は、
常には感じない強い危機感を覚えました。
怪我を負ったり、道に迷ったり、
ペース配分を誤って行動できなくなったりしたら、
遭難して命に関わるので、常よりも一歩を慎重に運び、
頻繁に地図を確認し、ペース配分にも気を配りました。
危機感があれば、それらの注意は自然と働くようでした
武術に関しても危機感の有無は、
当然、稽古の成否に直結するに違いないと思います。
ただそれは頭で分別されているだけで、
実感として迫ってきているかを自らに問えば、否です。
稽古のルールに守られている意識が先ずあり、
危機から来る注意の働きは鈍い状態です。
日常の生活に追われ流されて、
本当の危機から遠い位置に居る現状の見直しが必要なのだと、
強く感じました。
6. Posted by マルコビッチ 2013年03月19日 01:32
国によって考え方や習慣が違う・・・あるいは、
あの国は治安が良いとか悪いとか、それが具体的にどのようなことなのか、
どの程度のことなのか、あまりよく知らずに海外旅行に出かける。
私も調べることと言ったらガイドブックに載っている観光地や美味しい物ぐらいでした(^◇^;)
よその国とはこんなにも違うものなのかと驚きますが、いくらここで驚いても、
ニュースや実話をもとにした映画を観て衝撃を受けても、実際自分にはリアルではありません。
この平和な島国でノホホンと生きていたら、実際目の当たりにしていない衝撃は徐々に薄れていくのだと思うから・・
せめてこのブログや稽古を通して、自分の身は自分で守れるよう、あらゆる方向にアンテナをはり、正しいことにチューニング出来るよう自分自身に注意深くいたいと思います。
あの国は治安が良いとか悪いとか、それが具体的にどのようなことなのか、
どの程度のことなのか、あまりよく知らずに海外旅行に出かける。
私も調べることと言ったらガイドブックに載っている観光地や美味しい物ぐらいでした(^◇^;)
よその国とはこんなにも違うものなのかと驚きますが、いくらここで驚いても、
ニュースや実話をもとにした映画を観て衝撃を受けても、実際自分にはリアルではありません。
この平和な島国でノホホンと生きていたら、実際目の当たりにしていない衝撃は徐々に薄れていくのだと思うから・・
せめてこのブログや稽古を通して、自分の身は自分で守れるよう、あらゆる方向にアンテナをはり、正しいことにチューニング出来るよう自分自身に注意深くいたいと思います。
7. Posted by ユーカリ 2013年03月19日 17:14
ベネズエラの成人男性の死亡原因第一位が銃による殺害、またブラジルにおいてもアメリカよりも銃による死者数が多い事に、驚きました。
ずいぶん以前になりますが、ブラジルから日本に来たばかりの小学3年生の男の子に、何気なく
「日本はどう?」と質問したところ、「安全だからいい。ブラジルだと誘拐が結構ある。。。それと、給食がおいしくていい。」と即答したことに、随分驚き、私がそんな国で子供を育てるとなったら、どうしたら良いだろう…?とドキリッとしたことを思い出しました。
今、自分がどういう状況にあり、自身がどういう状態でいるのかを常に察知している事の重要性を日頃見逃してきてしまったのは、やはり、意識的に自分を内省し、意識的に物事に取り組んで来なかったからだなあ、と思います。
常に基本に忠実に、やっていることや扱っている物の意味を正しく理解して意識的にコツコツとそれに向かう事の難しさを痛感する日々です。
ただ、「どうしたらいいんだろ〜っ(・_・;)」と慌てているだけでは何も見えてこない・解決しない、という現実に、本当に恥ずかしながら、ようやく気づけた次第です。。。
いよいよ、射撃訓練ですね!わくわくしますっ(^^)
ずいぶん以前になりますが、ブラジルから日本に来たばかりの小学3年生の男の子に、何気なく
「日本はどう?」と質問したところ、「安全だからいい。ブラジルだと誘拐が結構ある。。。それと、給食がおいしくていい。」と即答したことに、随分驚き、私がそんな国で子供を育てるとなったら、どうしたら良いだろう…?とドキリッとしたことを思い出しました。
今、自分がどういう状況にあり、自身がどういう状態でいるのかを常に察知している事の重要性を日頃見逃してきてしまったのは、やはり、意識的に自分を内省し、意識的に物事に取り組んで来なかったからだなあ、と思います。
常に基本に忠実に、やっていることや扱っている物の意味を正しく理解して意識的にコツコツとそれに向かう事の難しさを痛感する日々です。
ただ、「どうしたらいいんだろ〜っ(・_・;)」と慌てているだけでは何も見えてこない・解決しない、という現実に、本当に恥ずかしながら、ようやく気づけた次第です。。。
いよいよ、射撃訓練ですね!わくわくしますっ(^^)
8. Posted by tetsu 2013年03月21日 14:08
服部君の事件は自分もよく覚えており、その事件を知った当時は日本人としてはショックな出来事でした。
ただ、自分もこうして武道を学んできて、また武藝館で、このブログで真の武術、、本当の戦い、心構えというものを学び改めて考え直してみると、やはり相手(文化や背景、国民性など)を知る、そして目の前にある危機や状況に素早く対応することがいかに大切かと強く思います。
つい最近日本でも駅前で刃物を振り回し、ケガ人が出た事件や、広島のカキ養殖場で中国人実習生が暴れそこの社長はじめ2人が殺されてしまった事件がありました。
「大丈夫だろう」「何でもないだろう」と今まで当たり前と思っている平和な社会とは、実は自分たちが勝手に思い込んでいるだけであって、「危険というものは常に隣り合わせにあるのだ」との認識を持たねばならないと強く感じます。
ただ、自分もこうして武道を学んできて、また武藝館で、このブログで真の武術、、本当の戦い、心構えというものを学び改めて考え直してみると、やはり相手(文化や背景、国民性など)を知る、そして目の前にある危機や状況に素早く対応することがいかに大切かと強く思います。
つい最近日本でも駅前で刃物を振り回し、ケガ人が出た事件や、広島のカキ養殖場で中国人実習生が暴れそこの社長はじめ2人が殺されてしまった事件がありました。
「大丈夫だろう」「何でもないだろう」と今まで当たり前と思っている平和な社会とは、実は自分たちが勝手に思い込んでいるだけであって、「危険というものは常に隣り合わせにあるのだ」との認識を持たねばならないと強く感じます。
9. Posted by 春日敬之 2013年03月26日 00:09
☆ bamboo さん
「龍の道」ではまだ紹介していませんが(たぶん・・)、
神戸に行かれたら、「神戸北野ホテル」の朝食がオススメです。
シェフ;ベルナール・ロワゾーの、「世界一の朝食」と賞される、
ヨーロピアン・ブレックファーストを、ぜひお試し頂きたいものです。
北野ホテルでは、本格的なフレンチ・ディナーも予約できますが、
ダイニングカフェで気軽にランチやディナーを楽しむこともできます。
いずれにしても、人気のオーベルジュですから予約をされ方が良いと思います。
あと、今時分なら元町の商店街にあるユーハイムの店頭で、
そこでしか売られていない「ミートパイ」があるかも知れません。
元町の商店街を入って行くと、本高砂屋の「きんつば」があります。
これを食べたら、他所のきんつばがバカバカしくて食べられないと言われるほどで、
私は神戸に行くときは、焼きたてをひとつ買って、歩きながら食べたりします。
ご案内したいことはいくらでもありますが、
自分で出会ったり発見することが旅の醍醐味ですから、このへんで。。。(^_^)
どうか楽しんできて下さいね。
「龍の道」ではまだ紹介していませんが(たぶん・・)、
神戸に行かれたら、「神戸北野ホテル」の朝食がオススメです。
シェフ;ベルナール・ロワゾーの、「世界一の朝食」と賞される、
ヨーロピアン・ブレックファーストを、ぜひお試し頂きたいものです。
北野ホテルでは、本格的なフレンチ・ディナーも予約できますが、
ダイニングカフェで気軽にランチやディナーを楽しむこともできます。
いずれにしても、人気のオーベルジュですから予約をされ方が良いと思います。
あと、今時分なら元町の商店街にあるユーハイムの店頭で、
そこでしか売られていない「ミートパイ」があるかも知れません。
元町の商店街を入って行くと、本高砂屋の「きんつば」があります。
これを食べたら、他所のきんつばがバカバカしくて食べられないと言われるほどで、
私は神戸に行くときは、焼きたてをひとつ買って、歩きながら食べたりします。
ご案内したいことはいくらでもありますが、
自分で出会ったり発見することが旅の醍醐味ですから、このへんで。。。(^_^)
どうか楽しんできて下さいね。
10. Posted by 春日敬之 2013年03月26日 00:09
☆玄花さん
日本が銃の所持を厳しく規制しているからと言って、
日本人が銃社会に無頓着で良い、ということにはなりませんね。
まして、その無関心や無頓着さがそのまま平和に繋がるわけでも無し。
玄花さんのように、職業としてライフルやナイフの訓練をしている人の方が、
武器についての正しい意味や意義を明確に認識できますね。
憧れや趣味で銃をいじっている人間、
武器を持つことで自分が強くなると錯覚してしまう人間が一番危険だと思います。
日本が銃の所持を厳しく規制しているからと言って、
日本人が銃社会に無頓着で良い、ということにはなりませんね。
まして、その無関心や無頓着さがそのまま平和に繋がるわけでも無し。
玄花さんのように、職業としてライフルやナイフの訓練をしている人の方が、
武器についての正しい意味や意義を明確に認識できますね。
憧れや趣味で銃をいじっている人間、
武器を持つことで自分が強くなると錯覚してしまう人間が一番危険だと思います。
11. Posted by 春日敬之 2013年03月26日 00:10
☆まっつさん
>それは頭で分別されているだけで
>実感として迫ってきているかを自らに問えば、否です
「稽古では実戦のように、実戦では稽古のように動ける者こそ、実戦で最も強い人間である」
と、よく先輩に言われました。
「常在戦場」は、かの山本五十六元帥の座右の銘でもあります。
稽古では、各々の練功に課題があり、
対練も相手を痛めつけることが目的ではないので、
つい危機感を実感することが希薄になりがちかも知れませんが、
日々の稽古でこそ、その「危機感を持つ訓練」をしなくては、
たとえどのような高度な稽古を学んでいても、
イザという時には何の役にも立たないものになってしまうことでしょう。
私の経験では、実戦に強い人は稽古ではとても優しい人が多いですが、
その人が稽古に向かう「意識」は、やはり一般人を抜いて遥かに高く、
どのような訓練でも、常に実戦を想定して行っていることが分かります。
>本当の危機から遠い位置にいる現状
・・というのは、
たとえ「趣味の単独登山行レベルの危機感」さえ存在しないような生活を送っていても、
或いは極端に、軍事的な仕事としての「今そこにある危機」が存在しなくとも、
自分の意識次第で、いくらでも訓練することが出来る、
いや、それを「平時」に訓練できる意識があるかどうかで決まる、
というコトですね。
>それは頭で分別されているだけで
>実感として迫ってきているかを自らに問えば、否です
「稽古では実戦のように、実戦では稽古のように動ける者こそ、実戦で最も強い人間である」
と、よく先輩に言われました。
「常在戦場」は、かの山本五十六元帥の座右の銘でもあります。
稽古では、各々の練功に課題があり、
対練も相手を痛めつけることが目的ではないので、
つい危機感を実感することが希薄になりがちかも知れませんが、
日々の稽古でこそ、その「危機感を持つ訓練」をしなくては、
たとえどのような高度な稽古を学んでいても、
イザという時には何の役にも立たないものになってしまうことでしょう。
私の経験では、実戦に強い人は稽古ではとても優しい人が多いですが、
その人が稽古に向かう「意識」は、やはり一般人を抜いて遥かに高く、
どのような訓練でも、常に実戦を想定して行っていることが分かります。
>本当の危機から遠い位置にいる現状
・・というのは、
たとえ「趣味の単独登山行レベルの危機感」さえ存在しないような生活を送っていても、
或いは極端に、軍事的な仕事としての「今そこにある危機」が存在しなくとも、
自分の意識次第で、いくらでも訓練することが出来る、
いや、それを「平時」に訓練できる意識があるかどうかで決まる、
というコトですね。
12. Posted by 春日敬之 2013年03月26日 00:10
☆太郎冠者さん
>動いた時に自然と型のような動きが出るのは・・
これですよ、コレ。
これこそが武術を学ぶ者が体得しなければいけない事なのです。
型の稽古は、確かに重要です。
武術には型しか無い、と言い切る方まで居られるように、
型を学ぶことで得られるものは計り知れません。
しかし、型のカタチを超えて、
型でないもの、つまり「無形」に至らなければ、実戦では使い物にはならない。
その無形に至るために、ひたすら「型」を訓練するわけですが、
ウチでは「無形」が自然に出て来るような稽古方法が存在しています。
それは、太極武藝館がただ単に伝統武術を伝承するだけではなく、
軍隊の実戦的な訓練体系が入っている事に由来しています。
序でながら、いつか「本物の特殊部隊員は普通の人に見える」という話が出ましたが、
それはあくまでも「一般人から見ればそう見える」ということであって、
同業・同類の人間から見れば、ひと目見ただけで、
遠くからでも、すぐにそれと認識できるものなのです。
例えば、訓練を積んだプロは都会の雑踏を歩いていても、
「あの人は私服の刑事」「あの外人はレンジャー上がり」
「あれは自衛隊の特殊部隊」などと、すぐに言い当ててしまいます。
で、近づいてみると、確かに脇の下が膨らんでいたり、耳に肌色のイヤホンが挿してあったり、
よく見ると靴がベイツのスニーカータイプだったりする・・・
しかし、普通の人は特殊部隊の人間が同じ「普通の人」に見えてしまい、
すっかり騙されて(?)しまいます。
それも、ある意味では彼らが「無形」を訓練しているからなのでしょうね。
まあ、そうでなくては「特殊」と名の付く仕事など、出来ませんが。
>動いた時に自然と型のような動きが出るのは・・
これですよ、コレ。
これこそが武術を学ぶ者が体得しなければいけない事なのです。
型の稽古は、確かに重要です。
武術には型しか無い、と言い切る方まで居られるように、
型を学ぶことで得られるものは計り知れません。
しかし、型のカタチを超えて、
型でないもの、つまり「無形」に至らなければ、実戦では使い物にはならない。
その無形に至るために、ひたすら「型」を訓練するわけですが、
ウチでは「無形」が自然に出て来るような稽古方法が存在しています。
それは、太極武藝館がただ単に伝統武術を伝承するだけではなく、
軍隊の実戦的な訓練体系が入っている事に由来しています。
序でながら、いつか「本物の特殊部隊員は普通の人に見える」という話が出ましたが、
それはあくまでも「一般人から見ればそう見える」ということであって、
同業・同類の人間から見れば、ひと目見ただけで、
遠くからでも、すぐにそれと認識できるものなのです。
例えば、訓練を積んだプロは都会の雑踏を歩いていても、
「あの人は私服の刑事」「あの外人はレンジャー上がり」
「あれは自衛隊の特殊部隊」などと、すぐに言い当ててしまいます。
で、近づいてみると、確かに脇の下が膨らんでいたり、耳に肌色のイヤホンが挿してあったり、
よく見ると靴がベイツのスニーカータイプだったりする・・・
しかし、普通の人は特殊部隊の人間が同じ「普通の人」に見えてしまい、
すっかり騙されて(?)しまいます。
それも、ある意味では彼らが「無形」を訓練しているからなのでしょうね。
まあ、そうでなくては「特殊」と名の付く仕事など、出来ませんが。
13. Posted by 春日敬之 2013年03月26日 00:10
☆とび猿さん
>当時田舎では・・・
確かに、古き良き日本がありましたですねぇ・・・
因みに、これは日本だけのことではなくて、外国でも田舎に行くと同じです。(笑)
私なんか、旅行者なのに、道を聞きに訪ねただけでも、まあ寄って行けと言われて、
ワインや食事をご馳走になった挙げ句、その家に泊まらせて頂くことになった経験があります。
>日本人の状況も変わってきていると感じます
そうですね。
日本を取り巻く世界の状況や、日本の中に存在している侵略の状況、
それらを知ることが、きちんと正しく危機感を持つことにつながると思います。
>当時田舎では・・・
確かに、古き良き日本がありましたですねぇ・・・
因みに、これは日本だけのことではなくて、外国でも田舎に行くと同じです。(笑)
私なんか、旅行者なのに、道を聞きに訪ねただけでも、まあ寄って行けと言われて、
ワインや食事をご馳走になった挙げ句、その家に泊まらせて頂くことになった経験があります。
>日本人の状況も変わってきていると感じます
そうですね。
日本を取り巻く世界の状況や、日本の中に存在している侵略の状況、
それらを知ることが、きちんと正しく危機感を持つことにつながると思います。
14. Posted by 春日敬之 2013年03月26日 00:11
☆マルコビッチさん
海外でも治安の悪い国はいくらでもありますね。
日本人が安全だと思っている有名な国々でも、
危険な他国の人間がその国に入っている場合には、
殺人や誘拐、人身売買などが日常的に行われているのが現状です。
旅行会社ではそこまでは教えてくれませんし、彼ら自身もそんな情報を受け取ってはいません。
たとえば、パリやロンドンのどの地区は危険だとか、
ブラジルのどの地区から誘拐されて消えた旅行者が多いかなどは、
普通の日本人は知らされていないと思います。
これは現代という時代だからではなく、
時や所や人種は変わっても、これまでもずっとそうだったワケです。
「人間」がどうであるかを識ること、
敵を知り、己を知り、世界を知ること、
これが最も必要とされることだと、ぼくは思います。
海外でも治安の悪い国はいくらでもありますね。
日本人が安全だと思っている有名な国々でも、
危険な他国の人間がその国に入っている場合には、
殺人や誘拐、人身売買などが日常的に行われているのが現状です。
旅行会社ではそこまでは教えてくれませんし、彼ら自身もそんな情報を受け取ってはいません。
たとえば、パリやロンドンのどの地区は危険だとか、
ブラジルのどの地区から誘拐されて消えた旅行者が多いかなどは、
普通の日本人は知らされていないと思います。
これは現代という時代だからではなく、
時や所や人種は変わっても、これまでもずっとそうだったワケです。
「人間」がどうであるかを識ること、
敵を知り、己を知り、世界を知ること、
これが最も必要とされることだと、ぼくは思います。
15. Posted by 春日敬之 2013年03月26日 00:11
☆ユーカリさん
ブラジルの街の危険性と、彼の国の食べ物の不味さは定評があります。
情熱の国、コーヒーとサッカーとブラジリアン柔術、
リオのカーニバルやコパカバーナの美しい景観をイメージしていると、
ブラジルの子供たちに蔓延している盗み、恐喝、麻薬、の実体がわからず、
旅行者として酷い目に遭わないための「心構え」など、全く消し飛んでしまいます。
まあ、上でマルコビッチさんに申し上げたとおりです。
>意識的にコツコツとそれに向かう事の難しさを痛感する日々です
「コツコツとそれに向かうこと」が難しいのではなく、
「意識的になること」が難しいのです。
意識的になることは、訓練によってしか身に付きません。
訓練とは、「そうでないもの」を「そうなる」ように導くことです。
だから、意識が必要とされる「道」と「指導者」が必要となるのです。
武術でも、禅でも、
茶道も、華道も、剣道も、書道も、
「道」と名の付くありとあらゆる修行も、
みな同じことです。
ブラジルの街の危険性と、彼の国の食べ物の不味さは定評があります。
情熱の国、コーヒーとサッカーとブラジリアン柔術、
リオのカーニバルやコパカバーナの美しい景観をイメージしていると、
ブラジルの子供たちに蔓延している盗み、恐喝、麻薬、の実体がわからず、
旅行者として酷い目に遭わないための「心構え」など、全く消し飛んでしまいます。
まあ、上でマルコビッチさんに申し上げたとおりです。
>意識的にコツコツとそれに向かう事の難しさを痛感する日々です
「コツコツとそれに向かうこと」が難しいのではなく、
「意識的になること」が難しいのです。
意識的になることは、訓練によってしか身に付きません。
訓練とは、「そうでないもの」を「そうなる」ように導くことです。
だから、意識が必要とされる「道」と「指導者」が必要となるのです。
武術でも、禅でも、
茶道も、華道も、剣道も、書道も、
「道」と名の付くありとあらゆる修行も、
みな同じことです。
16. Posted by 春日敬之 2013年03月26日 00:12
☆ tetsu さん
そう、私たちが当たり前だと思ってきた平和な社会は、
実は、とんでもない危険がすぐ隣り合わせにある、危ない社会なのでした。
それを意識できるようにするためにも、
本格的な本物の武術を学ぶ意義は大きいと思います。
太極武藝館では、とくに研究會以上のクラスでは、
これまでにも増して実戦を想定した訓練が行われるようになりました。
それは「太極拳の実戦用法」などという陳腐なものではなく、
円山館長と玄花后嗣の実際の経験による、
軍隊や特殊部隊で行われている訓練法が取り入れられたものです。
今後の稽古も、大いに期待すべきものと思います。
そう、私たちが当たり前だと思ってきた平和な社会は、
実は、とんでもない危険がすぐ隣り合わせにある、危ない社会なのでした。
それを意識できるようにするためにも、
本格的な本物の武術を学ぶ意義は大きいと思います。
太極武藝館では、とくに研究會以上のクラスでは、
これまでにも増して実戦を想定した訓練が行われるようになりました。
それは「太極拳の実戦用法」などという陳腐なものではなく、
円山館長と玄花后嗣の実際の経験による、
軍隊や特殊部隊で行われている訓練法が取り入れられたものです。
今後の稽古も、大いに期待すべきものと思います。
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。